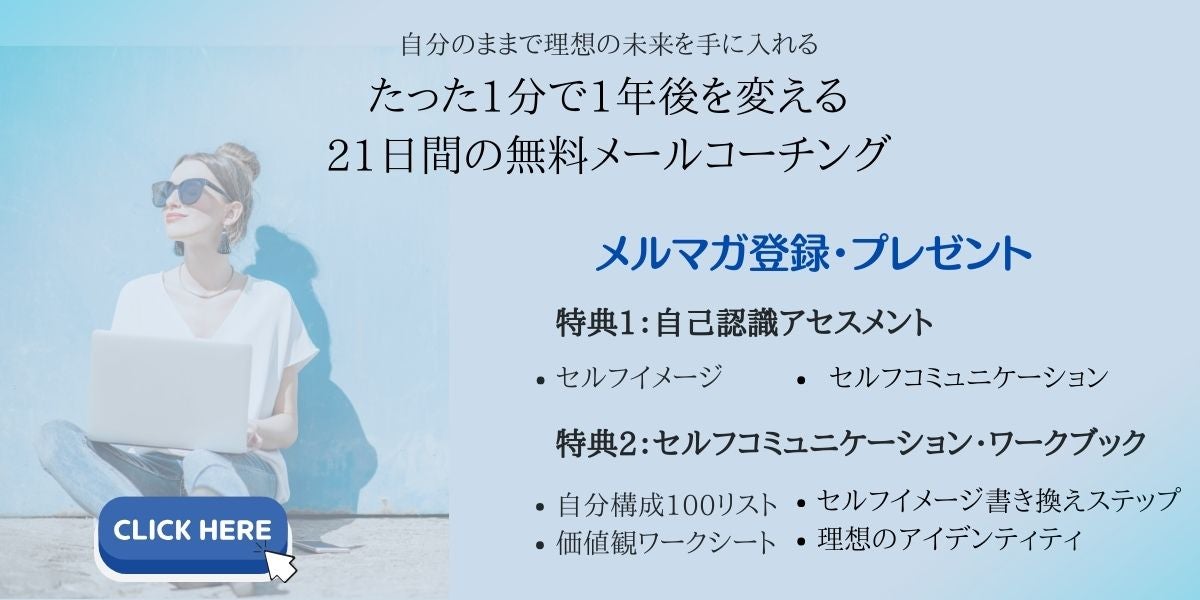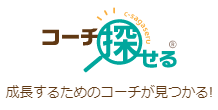自分との付き合いかた。
自分コミュニケーション。
一番の幸せは、自分との繋がり感・安心感。
自分が感じる感情をすべてOKとして、
どんな感情を感じても大丈夫なんだ。
と安心して感じられる感覚。
それがベースにあることで、
安心感の元で未来を描ける。
自分で自分の未来を創れるという体感。
私も紆余曲折的な人生を
全部自分で創ってきたんだぁ~
って腑に落ちたあたりから
欲のまま、望み出しをして
叶えられるようになってきました。
止めていたのは自分だったと
気付いたのは40代からです。
そして私のクライアント様も
多くが30代後半から40代。
今まで外側で頑張ってきて、
人生、いろいろを経験してきて、
自分の人生、自分自身に向き合いたい。
そんな思いからコーチつけられて
自分の土台作りから始めてもらってます。
自分の強みだけではなく弱みも見てあげる。
できていない自分をも見てあげる。
もしかしたら、行動し続けている方が
気持ち的に楽って感じることもある。
(私も行動している方が楽だった(-_-;))
これは、無意識なので気付かないけど
感じたくないこと、見たくない自分は
無意識に避けるような行動選択をする。
さらっとスルーする力が備わるのです。
そこは、スルーしちゃ、いけないとこ。
だって何よりも誰よりも
自分が自分のこと無視し続けてたら
豊かな幸せの流れに向かって行きません。
感情と向き合う、思い込みに気付く。
自分を認めて、受容し続けることで
コントロール不可能な外側の現実が
すこしづつ動き出すことを実感できます。
遅かれ早かれですが、
自分のために時間とお金を投資して
その投資をあなたの生きていく価値に
変えてあげてください。
その選択をできるのは
あなたしかいない。よね😊
今日も笑顔多めな1日を😊